

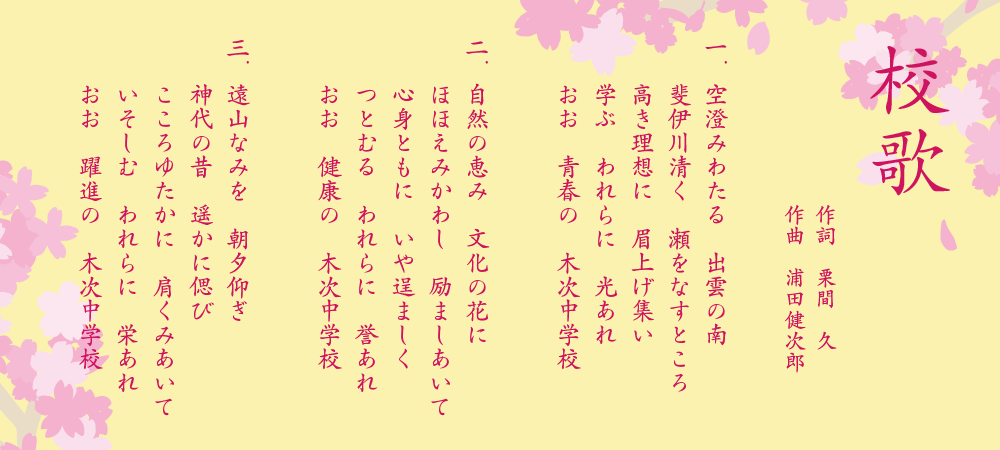
| 昭和50年4月1日 | 木次町立木次日登温泉三中学校が統合し、新市に校舎を新築 |
|---|---|
| 昭和60年10月11日 | 開校10周年記念式典 |
| 平成元年8月21日 | 全国中学校ソフトボール大会男子の部第3位 |
| 平成3年8月2日 | 島根県中学校優勝野球大会優勝 |
| 平成5年9月 1日 | コンピュータ教室竣工 |
| 平成6年7月22~25日 | 島根県中学校総合体育大会 総合第3位 |
| 平成7年10月29日 | 開校20周年記念式典 |
| 平成8年4月9日 | 部室棟竣工 |
| 平成11年7月23日 | 島根県中学校総合体育大会男子バレー部優勝 |
| 平成11年10月26日 | 文部省指定教育総合推進地域事業研究発表会 |
| 平成12~14年 | 文部科学省指定マルチメディア活用学校間連携推進事業 |
| 平成14年11月10日 | 少年の主張全国大会出場「青少年育成国民会議会長奨励賞」 |
| 平成15年2月28日 | 第62回全国教育美術展「文部科学大臣奨励賞」(全国学校賞) |
| 平成15~16年 | 文部科学省指定国語力向上モデル事業 |
| 平成15年8月2~3日 | 中国中学校ソフトボール大会男子の部 第1位 |
| 平成15年11月14日 | 武道場,屋内運動場整備竣工式 |
| 平成17年1月28日 | 文部科学省指定国語力向上モデル事業発表会 |
| 平成17年8月5~7日 | 中国バレーボール大会 男子ベスト8 |
| 平成17年8月5~7日 | 中国ソフトボール大会 男子準優勝、女子第3位 |
| 平成17年10月30日 | 統合30周年記念式典、祝賀会 |
| 平成18年度~ | 教育支援コーディネーター配置(中学校駐在) |
| 平成19年2月4日 | 全日本アンサンブルコンテスト中国大会 フルート四重奏銀賞 |
| 平成19年6月3日 | 島根県少年野球大会 木次中学校クラブ優勝 |
| 平成20年7月~ | 地域コーディネーター配置(雲南市全小中学校) |
| 平成21年4月~ | 夢発見プログラム、「お弁当の日」スタート |
| 平成23年11月 | 少年の主張全国コンクール奨励賞 |
| 平成24年10月 | 校舎耐震改修工事完了 |
| 平成25年11月 | 雲南市教育研究大会会場校として授業公開 |
| 平成26年 8月 | 普通教室へのエアコン設置 |
| 平成27年~平成29年 | 自転車マナーアップモデル校指定 |
| 平成27年 10月31日 | 統合40周年記念式典、祝賀会 |
| 平成27年 11月 | 「メディアリテラシーのための調査・研究」県表彰 |
| 平成28年 1月 | 「竹島・北方領土問題を考える」中学生作文コンクール学校賞 |
| 平成28年 2月 | 「北方領土に関する全国スピーチコンテスト」全国3位 |
| 平成29年 2月 | 「北方領土に関する全国スピーチコンテスト」全国2位 |
| 平成30年 2月 | 「竹島・北方領土問題を考える」中学生作文コンクール学校賞 |
| 平成31年 2月 | 「北方領土に関する全国スピーチコンテスト」全国2位 |
| 令和元年 | 全日本教育工学研究協議会全国大会島根大会で授業公開 島根県中学校優勝野球大会 準優勝 中国大会ベスト8 「竹島・北方領土問題を考える中学生作文コンクール」島根県竹島・北方領土問題教育者会議会長賞 「明るい選挙啓発ポスターコンクール」文部科学大臣賞・総務大臣賞(第一席)、加納勇一賞 |
| 令和2年 | 新型コロナウイルス感染症のため、臨時休業、県総体等中止になる。 |
| 令和3年 | 「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善プロジェクト事業授業研究会 GIGAスクール構想タブレット端末配付 新型コロナウイルス感染症のため、臨時休業 |
| 令和4年 | 島根県中学校優勝野球大会準優勝 中国大会出場 少年の主張雲南市大会最優秀賞 新型コロナウイルス感染症のため、臨時休業 修学旅行(県外2泊3日を3年ぶりに実施)
|
| 令和5年 | 中国中学校総体ソフトボールの部出場 中国中学校剣道選手権女子個人の部出場 少年の主張全国大会奨励賞受賞 |
| 令和6年 | 中国中学校総体ソフトボールの部出場 少年の主張全国大会奨励賞受賞 創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 中国中学バレーボール新人大会男子の部出場 読書感想画中央コンクール奨励賞受賞 |
〇基礎・基本を身につけ、学び合い高め合う生徒 (課題対応能力)
〇違いを尊重し、思いやりと感謝の心をもって行動できる生徒(人間関係形成能力・社会形成能力)
〇心身共に健康で、たくましく生きようとする生徒(自己理解・自己管理能力)
〇志を高く持ち、その実現に向かって努力する生徒(キャリアプランニング能力)
○生徒一人一人を大切にし、生徒とともに向上していこうとする教職員
○指導力・人間力の向上に向けて学び合い、研鑽し続ける教職員集団
○対話と敬愛に基づき互いのよさや強みを生かしてチームワークを高める教職員
〇教育公務員としての自覚と誇りをもち、教育目標達成に向けて協働する教職員
【めざす学校像】
〇安心・安全な学校
▶生徒・職員が安心・安全に生活できる環境づくり
〇あたたかく活力ある学校
▶キャリア教育の視点を持ち、温かな信頼関係と活力を育む教育の推進
〇力を伸ばす学校
▶豊かな心、確かな学力、逞しい体を育む創意工夫のある教育の推進
〇信頼され協働する学校
▶学校・家庭・地域との連携・協働に基づく教育の推進
(1)豊かな心の育成
〇自尊感情を高め、自分・学校・地域に誇りをもてる教育活動の展開
〇「自律の力」を育む生徒主体の自主的・創造的な活動の推進
〇違いを認め合い、支え合い高め合う集団づくり
〇学校・家庭・地域の連携による生き方教育(「志教育」)の推進
〇全ての教育活動を通じた人権・同和教育の充実と積極的な推進
(2)特別支援教育の推進・生徒指導の充実
○多面的な生徒理解に基づく、個に応じた指導・支援の充実と積極的な生徒指導の推進
(3)確かな学力の育成
〇主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
〇特別支援教育の視点を踏まえたユニバーサルデザインの授業づくり
〇学校図書館、ICTを効果的に活用した学習指導、読書指導の推進
(4)健やかでたくましい体づくり
〇感染症予防、防災対応等の自己管理能力の育成 ”自分の身は自分で守る”力の育成
〇授業、部活動等を通した、主体的に体力向上を図る取組の推進
〇安全教育、性教育、食と睡眠、メディア教育等の推進
(5)信頼される学校づくり
〇学校運営協議会や関係機関と連携した生徒の健全育成に向けた取組の充実
○生徒の成長を促す地域貢献、地域連携の推進(職場体験、Go to ボランティア等)
〇「木次の子どもを育てる会」を通した保幼こ小中連携の取組の推進
○統合50周年を節目とした家庭・地域へのさらなる情報発信と協働の推進
R7 研究推進
・ねらいを明確にした指導計画の作成
・様々な課題を発見・分析し、計画を立てて解決しようとする課題解決的な学習の展開
・カリキュラムマネジメントによる教科等を関連させた指導過程の工夫
・必要感のある「伝え合う場」の設定
・学習形態(個、ペア、グループ、全体)に応じた「話すこと・聞くこと」の指導
・伝え合う力を高めるためのICT機器、付箋紙、ミニボード等の有効活用
・意図的・計画的な情報活用能力の育成のためのカリキュラムマネジメントの実施
・目的意識、相手意識を重視した、プレゼンテーションやレポート、新聞等の作成
・ICT機器や学校図書館の有効活用
| ○日頃から教職員と生徒との信頼関係の構築に努める。 ○教職員は常にいじめを疑う目をもち、生徒の小さな変化(健康観察・授業・給食・清掃・休憩・部活動などの時間に複数の教員の目で観察するとともに、日々の「生活ノート」での生徒のコメントなど)を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を高める。 ○教職員間で情報を共有し、保護者や地域の方と連携して情報収集に努める。 |
| ○24時間子供SOSダイヤル ○子どもの人権110番 ○いのちの電話 ○児童相談書虐待対応ダイヤル |
0120-0-78310 0120-007-110 0570-783-556 189 |
| 〈構成員〉 校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、生徒支援担当 |
| 〈構成員〉校長・教頭・生徒指導主事・該当学年主任・該当担任・生徒支援担当・該当部活動顧問など |
| 〈生命の心身又は財産に重大な被害とは〉 ・生徒が自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合 ・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合 |
| 〈 調査結果の提供・報告 〉 被害生徒・保護者に対して、以下のことを説明する。 ・調査の目的・目標 ・調査主体(組織の構成、人選) ・調査時期・期間 ・調査事項 ・調査方法 ・調査結果の提供 情報の提供において、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。 |
| 学校で起こり得る事例の例 | 該当し得る犯罪 |
| 〇ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生などを殴ったり、蹴ったりする。 〇無理やりズボンを脱がす。 |
暴 行 |
| 〇感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生などを切りつけてけがをさせる。 | 傷 害 |
| 〇断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻を触る。 | 強制わいせつ |
| 〇断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。 〇断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。 |
恐 喝 |
| 〇本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。 | 脅 迫 |
| 〇特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて、身体的特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工などと悪口を書く。 | 名誉棄損・侮辱 |
| 〇同級生などに対して「死ね」と言ってそそのかし、その同級生などが自殺を決意して自殺した。 | 自殺関与 |
| 〇同級生などに対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影して送るよう指示し、自己のスマートフォンに送られる。 〇同級生などの裸の写真・動画を友達1人に送信して提供したり、SNS上のグループに送信して多数の者に提供する。 〇友達から送られてきた児童ポルノの写真・動画を、性的好奇心を満たす目的でスマートフォン等に保存している。 |
児童ポルノ提供等 |
| 〇元交際相手と別れた腹いせに性的な写真・動画をインターネット上に公表する。 | 私事性的画像記録提供(リベンジポルノ) |
|
月
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
2
|
3
|
||
|
平 日
|
18:30
|
|
18:00
|
17:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
|||||||
○木次中学校の特色を紹介し、教育活動について、保護者・地域等、広く理解と協力を得る。
○木次中学校の生徒の活動を公開し、その活動の素晴らしさをより多くの保護者・地域等に紹介する。
○ホームページ(学校所在地・地図、校舎写真、もくじ、2次元バーコード) ※電話・FAX・メールアドレスは公開しない。
○学校紹介、学校沿革史、生徒数の変遷、学級数
○年間行事予定・月別行事予定
○体育祭、文化祭、講演会などの学校公開のお知らせ
○教育課程・総合的な学習など教育内容の紹介
○部活動紹介
○大会予定・結果・表彰等
○学校便り(電子版)
○学校便り、アルバムは、パスワード閲覧とする。パスワードは年度ごとに改める。
○生徒とその保護者、および教職員の人権が侵害されるおそれのある情報は公開しない。
(住所、電話番号、生年月日、氏名などの個人情報は公開しない。)
○学校関係者以外の者が、容易に個人を特定できるような画像は公開しない。
(基本的に画像を公開する際には、顔が写っていないものや、画質を落として顔が明確に特定できないものを使用します。大会結果・表彰を公開する場合も個人名を伏せて公開します。)
○学校ウェブページの公開に関してセキュリティーポリシーを明示するとともに、写真掲載に関する承諾を得る。また生徒の作品(絵画・作文等)を公開する場合も、本人や保護者の承諾を得る。
(1)個人情報保護に関する必要な研修を受けたウェブ管理者を配置し、ウェブ更新に従事する。
(2)ウェブ管理者が作成した更新画面は、まずは校内サーバーで公開しチェックを受ける。
①該当情報の担当者→ ②教頭 → ③校長 の決裁を受けた後 アップする。(検印シートを回覧し、ウェブ画面更新の点検記録を残す。)
(3)公開後、生徒や保護者から要請があった場合には、情報発信の内容の「削除・変更」など速やかに対応する。また要請者に対してヒアリング調査を行う。