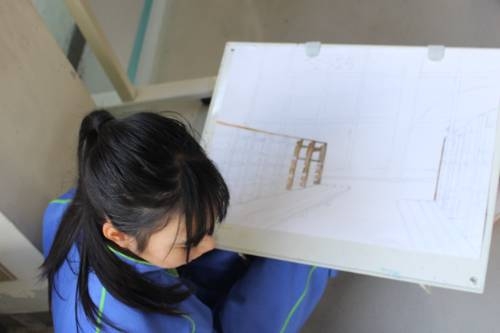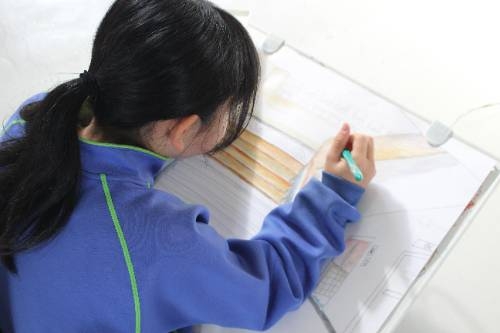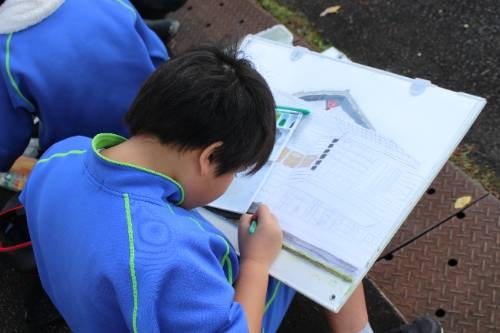5・6年生「平和学習」
2024-11-22 12:46:54






◇雲南市の遺族会の皆様においでいただいて、自分たちの身近な雲南市でも多くの戦争の爪痕が残っているお話を伺いました。戦争は決して自分たちの知らない遠い場所で起こっているのではなく、過去ではあっても、すぐ近くでたくさんの悲劇が起きていたのだという現実を学ぶことができました。以前にNHKで全国放送もされた、戦争遺児の方の戦時中に父親が出征したときや戦地からその父の訃報が届いた時の気持ちを語られた肉声を聴き、大きな衝撃を受けるとともに、改めて戦争の悲惨さや平和の尊さをかみしめる貴重な学びの場となりました。