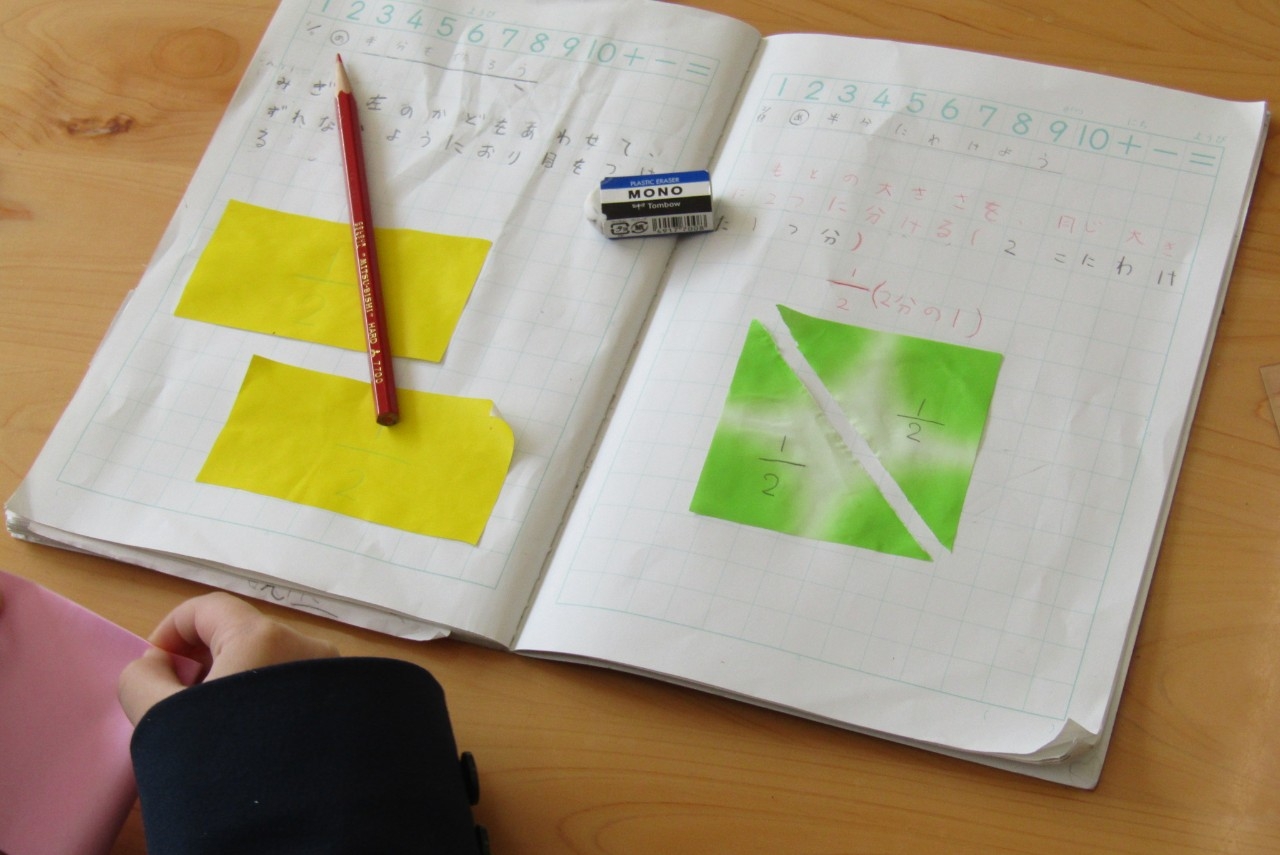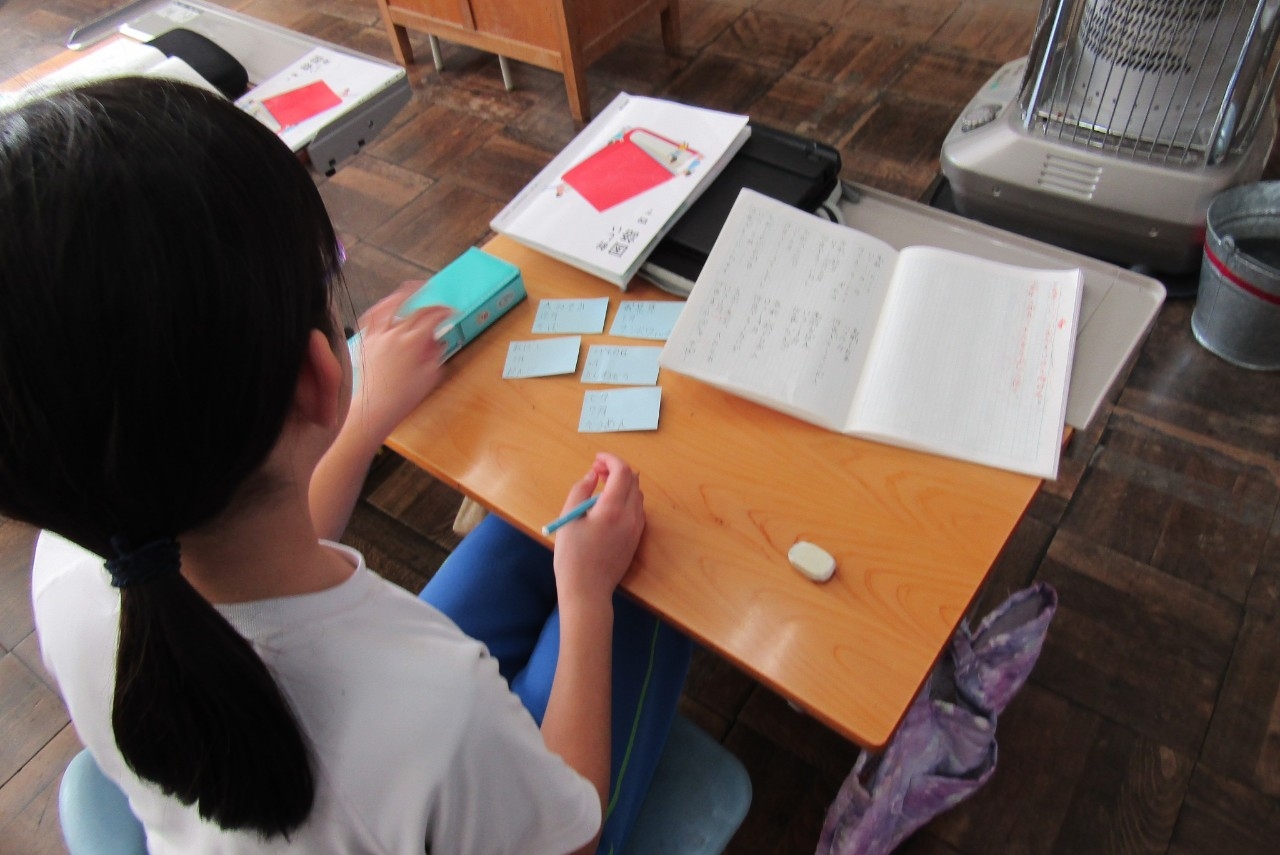ようこそ 小学校へ
2024-02-15 17:00:00






今日の昼休みに、近くの保育園の子たちが凧揚げにやってきました。大切に作った凧を思い切りとばしたいという思いを持ってやってきました。ちょうど、小学生は給食中で、最初は校長のみが関わっていました。「ねぇ、お兄ちゃんたちは何をしているの。」「給食ってお弁当なの。」「校長先生ってどんな仕事なの?」「私が入る学校の校長先生だよね。」などとたくさん話しかけてくれました。しかし、関心ごとは、1位は凧、2位は断然小学生でしたので、小学生に「時間があれば、校庭で保育園の子どもたちと遊んでみてください。」と声をかけました。
すると、3枚目の写真のようにほぼ全校の子どもたちが校庭に出ました。どう声をかけてよいのかがわからないのか、恥ずかしいのか、高学年の子どもたちは、保育園の子どもたちの周りで「こんにちは。」と集団で声をかけるくらいしかできなかったようです。4、5枚目の写真の6年生の子は、そんな中で、スーッと近寄って凧をもってあげていました。うまいかかわり方をしていました。
6年生は「全員が保育園の子たちとかかわるのは迷惑だから、鬼ごっこしようよ。」と声がけをしました。これも、園児が楽しめるためにできることの一つと考えたようです。
校庭から帰ってきた2年生の子が、「楽しかった。かわいかったよ。ぼくは大きくなったんだよ。」と言っていました。保育園の子たちが、小学校って楽しいなと思ってもらえたのかどうかは疑問ですが、楽しいひとときを過ごすことができました。
本校は、いつでもお待ちしております。どうぞ、お越しください。
すると、3枚目の写真のようにほぼ全校の子どもたちが校庭に出ました。どう声をかけてよいのかがわからないのか、恥ずかしいのか、高学年の子どもたちは、保育園の子どもたちの周りで「こんにちは。」と集団で声をかけるくらいしかできなかったようです。4、5枚目の写真の6年生の子は、そんな中で、スーッと近寄って凧をもってあげていました。うまいかかわり方をしていました。
6年生は「全員が保育園の子たちとかかわるのは迷惑だから、鬼ごっこしようよ。」と声がけをしました。これも、園児が楽しめるためにできることの一つと考えたようです。
校庭から帰ってきた2年生の子が、「楽しかった。かわいかったよ。ぼくは大きくなったんだよ。」と言っていました。保育園の子たちが、小学校って楽しいなと思ってもらえたのかどうかは疑問ですが、楽しいひとときを過ごすことができました。
本校は、いつでもお待ちしております。どうぞ、お越しください。