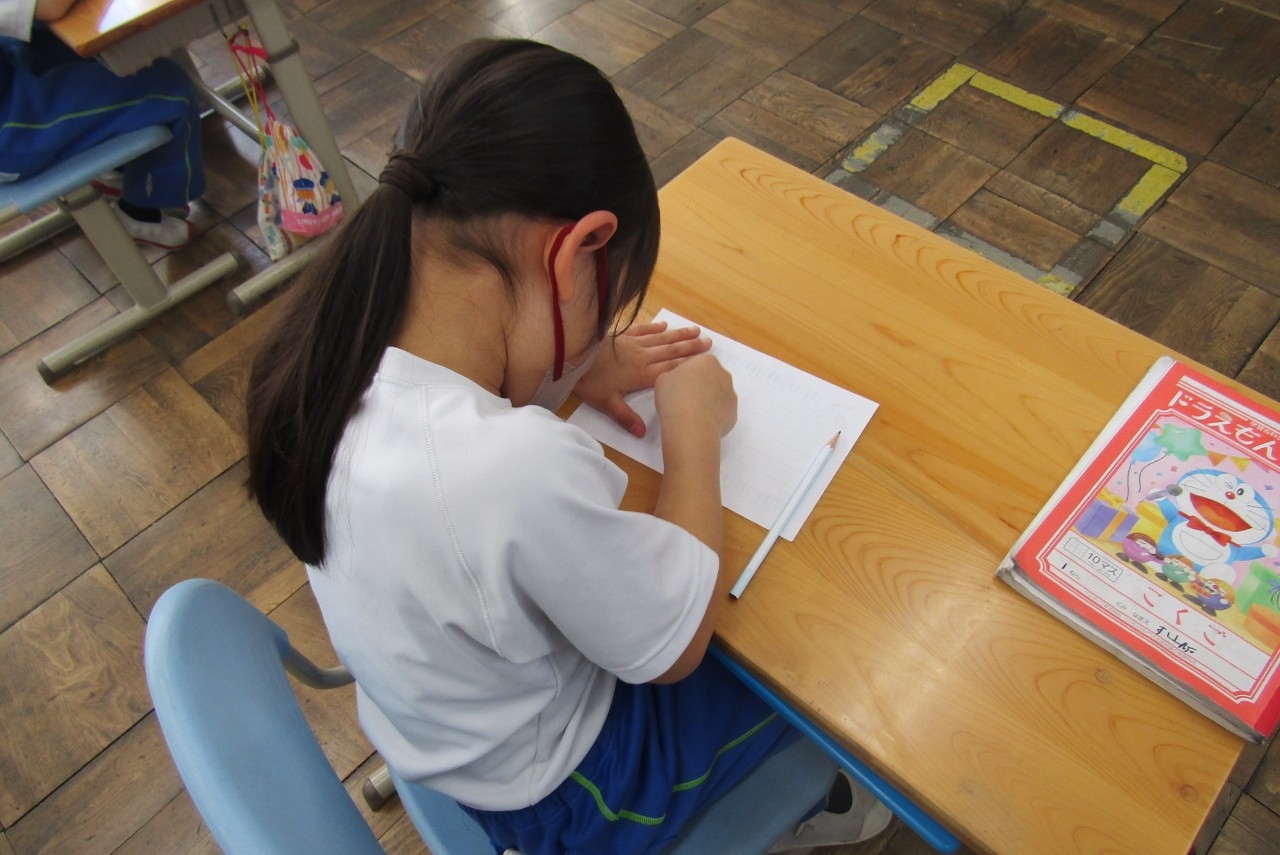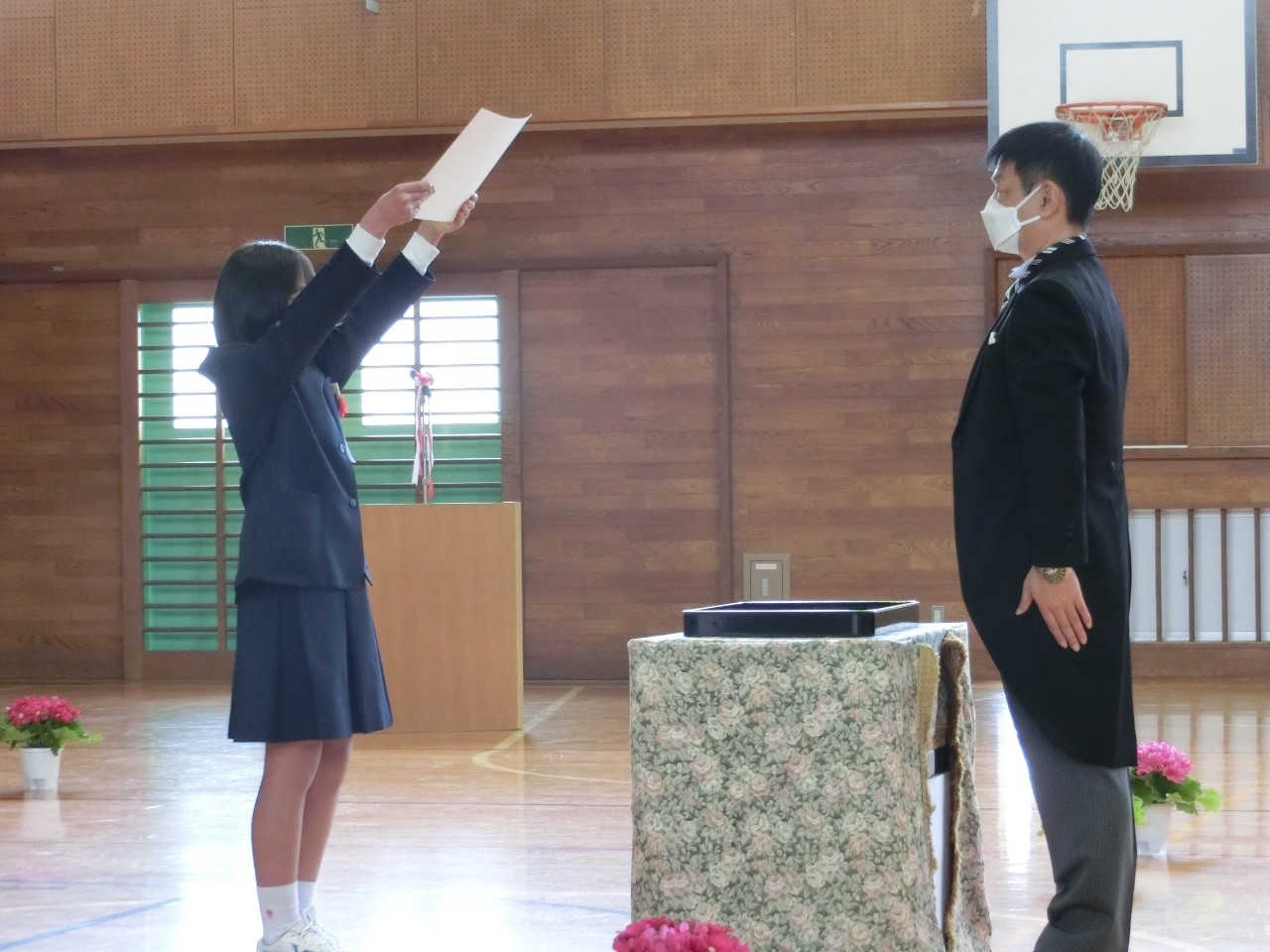1年間の集大成
2023-03-23 17:25:28






今日は、今年度最後の普通授業の日でした。昨日からいわゆる「お楽しみ会」を各学級が行っていました。職員室では、「あの子たちは、2時間の計画をしっかり立てるのかと思っていたら、びっちりみんなが楽しめるように企画していたんだよ」「『会で先生が準備するものは何か』と聞いて準備したものだけを用意したよ。それだけでうまくいくのか、わからないけれど、あるようにやるんじゃないのかな」という会話が聞こえました。
義務教育は、子どもが自律・自立できることをめざして行うものですので、年度の最後に子どもたちが自分たちの考えたことを、折り合いをつけながら実施することができている姿が見られれば、1年間しっかり育ったとうれしく思います。「お楽しみ会」のほかにも「大掃除」も同じです。子どもたちが率先して行うことができるとよく育ったと誇らしいと思います。
今日は、大東町内の給食を管理していただいていた栄養教諭の方、最後の給食でした。各クラスに回って紹介すると「残念だな。会えるといいな。」と別れを惜しんでいました。給食を毎日安全に運んでもらっている運転手さんとともに感謝する子どもたちがたくさんいたことも、「育っているな」とうれしくなる瞬間です。
最後の写真は、2年生が「オクラの種」を感謝の気持ちを込めてくれたプレゼントです。渡すときにとてもうれしそうな表情なので、もらった人はどの人も「ほっこり」した気分になりました。これも、「この子たちと1年間過ごしてきてよかったな」とうれしく思う瞬間です。
義務教育は、子どもが自律・自立できることをめざして行うものですので、年度の最後に子どもたちが自分たちの考えたことを、折り合いをつけながら実施することができている姿が見られれば、1年間しっかり育ったとうれしく思います。「お楽しみ会」のほかにも「大掃除」も同じです。子どもたちが率先して行うことができるとよく育ったと誇らしいと思います。
今日は、大東町内の給食を管理していただいていた栄養教諭の方、最後の給食でした。各クラスに回って紹介すると「残念だな。会えるといいな。」と別れを惜しんでいました。給食を毎日安全に運んでもらっている運転手さんとともに感謝する子どもたちがたくさんいたことも、「育っているな」とうれしくなる瞬間です。
最後の写真は、2年生が「オクラの種」を感謝の気持ちを込めてくれたプレゼントです。渡すときにとてもうれしそうな表情なので、もらった人はどの人も「ほっこり」した気分になりました。これも、「この子たちと1年間過ごしてきてよかったな」とうれしく思う瞬間です。