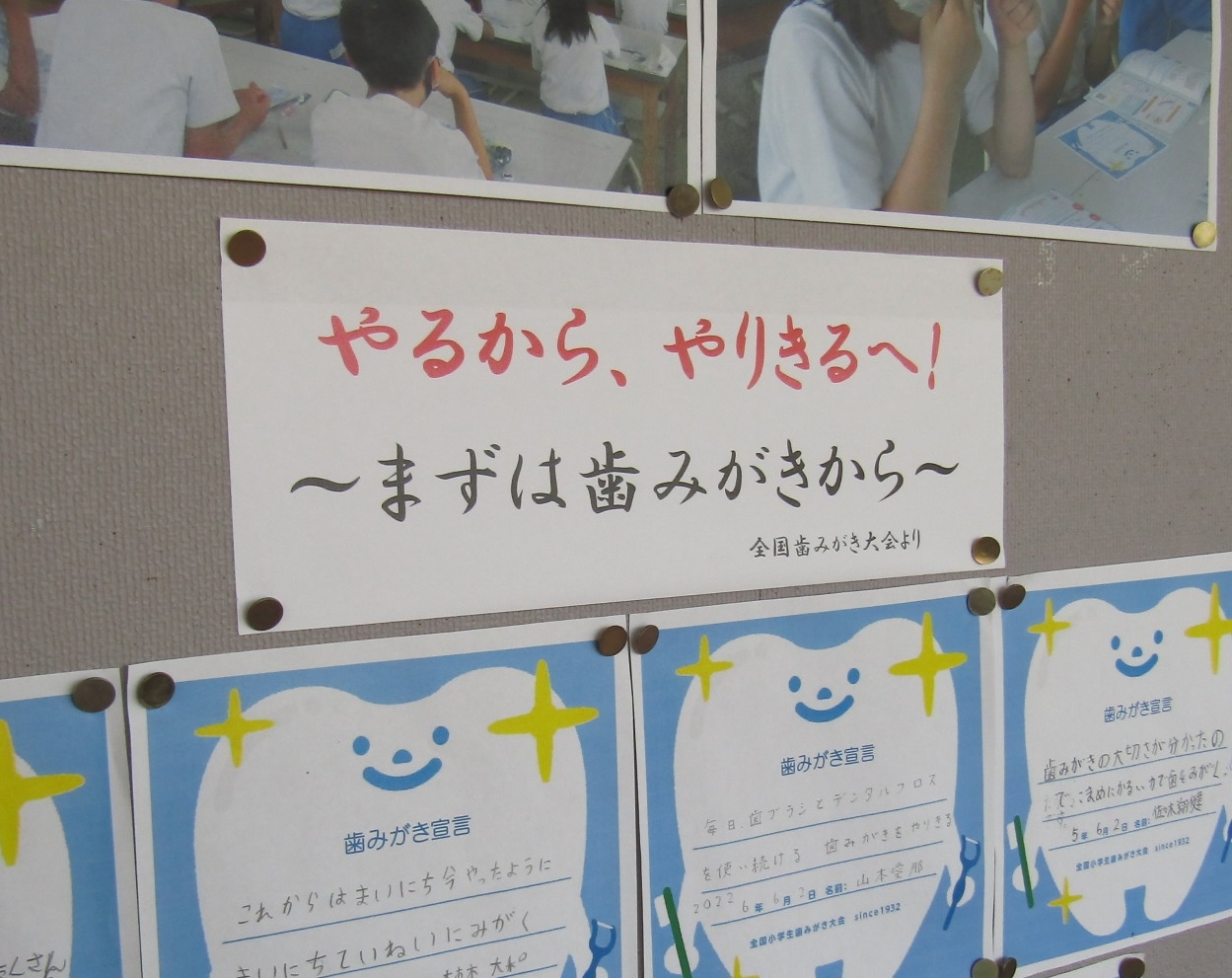つきつめて言えば・・・
2022-11-21 17:26:46






今日3年生の教室にいくと、算数の「小数の計算」の学習を行っていました。いつも、前向きな姿勢での学びが見られますが、より一層のやる気でした。0.4+0.5を考える際に、0.1が4つと5つをたすから0.1が9つ。だから0.9になるという考えをしていくと簡単だということを見つけ出した子どもたちは、「先生!次の問題をお願いします!」と言い出します。すかさず、0.7+0.3や0.8+0.4といった繰り上がりのある計算を担任は出します。3年生は、ペアやグループで自分の考えをしっかり話せるので、少々間違えても、苦にならなくなっています。「0.1が10個だから1だよね」「えっ、ぼくは1.0にしたよ。」「どちらも0.1が10個だから間違いじゃないと思うけど、どう?」などと会話が弾んでいます。こうして、自分たちで簡単に計算できるための考え方を導き出しているので、どんな問題を出されても「挑戦」していこうとしています。写真にはないですが、隣の4年生でも32✕20✕5を32✕(20✕5)で計算した方が簡単打ということを見つけ、その方法は正しいのかを確かめる活動を行っていました。算数は、ひとまとまりとして整理することや順番を変えたり、別の表し方にしたりして、より簡単にわかりやすくするにはどうすればよいのかを考えることが多いかも知れません。5+8を丸を13個かいて正解を導いていた子が、5+5と3でと10まとまりで考えることを見つけ出したとき、「算数って、いいよね。」と味わえるようです。
5枚目の写真は、2年生の国語、「ぼくの私のお気に入りを紹介しよう」の活動です。6枚目は、1年生の国語、「ぼくの私の好きな教科」の活動です。なぜお気に入りなのか(好きなのか)について、自分の気持ちをしっかり見つめて考えていました。そればかりならよいのですが、相手に伝わるようにしなければなりませんので、自分ばかりではなく友だちなどの他の人の気持ちも考えなくてはいけません。そうやって苦労して書いた紹介文ですので、「あぁ、なるほどね。」と言われると、自分のがんばり、自分のお気に入りや好きなものなどたくさんの「自分」を認めてもらえたことになります。国語の醍醐味ですね。
つきつめて言えば、算数ができるとか、国語ができるというより、考え方を変えるとか深めるということを算数や国語の時間に行っているということでしょう。
5枚目の写真は、2年生の国語、「ぼくの私のお気に入りを紹介しよう」の活動です。6枚目は、1年生の国語、「ぼくの私の好きな教科」の活動です。なぜお気に入りなのか(好きなのか)について、自分の気持ちをしっかり見つめて考えていました。そればかりならよいのですが、相手に伝わるようにしなければなりませんので、自分ばかりではなく友だちなどの他の人の気持ちも考えなくてはいけません。そうやって苦労して書いた紹介文ですので、「あぁ、なるほどね。」と言われると、自分のがんばり、自分のお気に入りや好きなものなどたくさんの「自分」を認めてもらえたことになります。国語の醍醐味ですね。
つきつめて言えば、算数ができるとか、国語ができるというより、考え方を変えるとか深めるということを算数や国語の時間に行っているということでしょう。