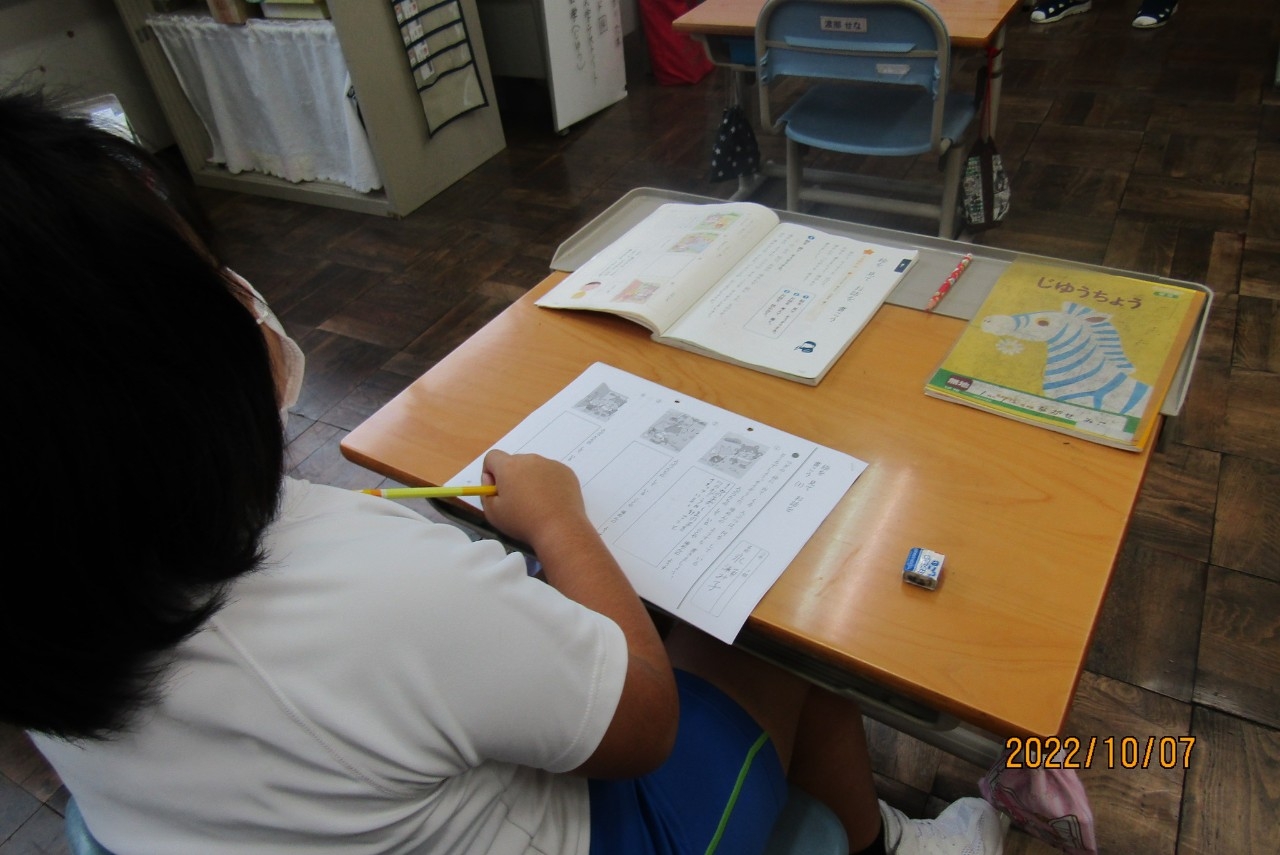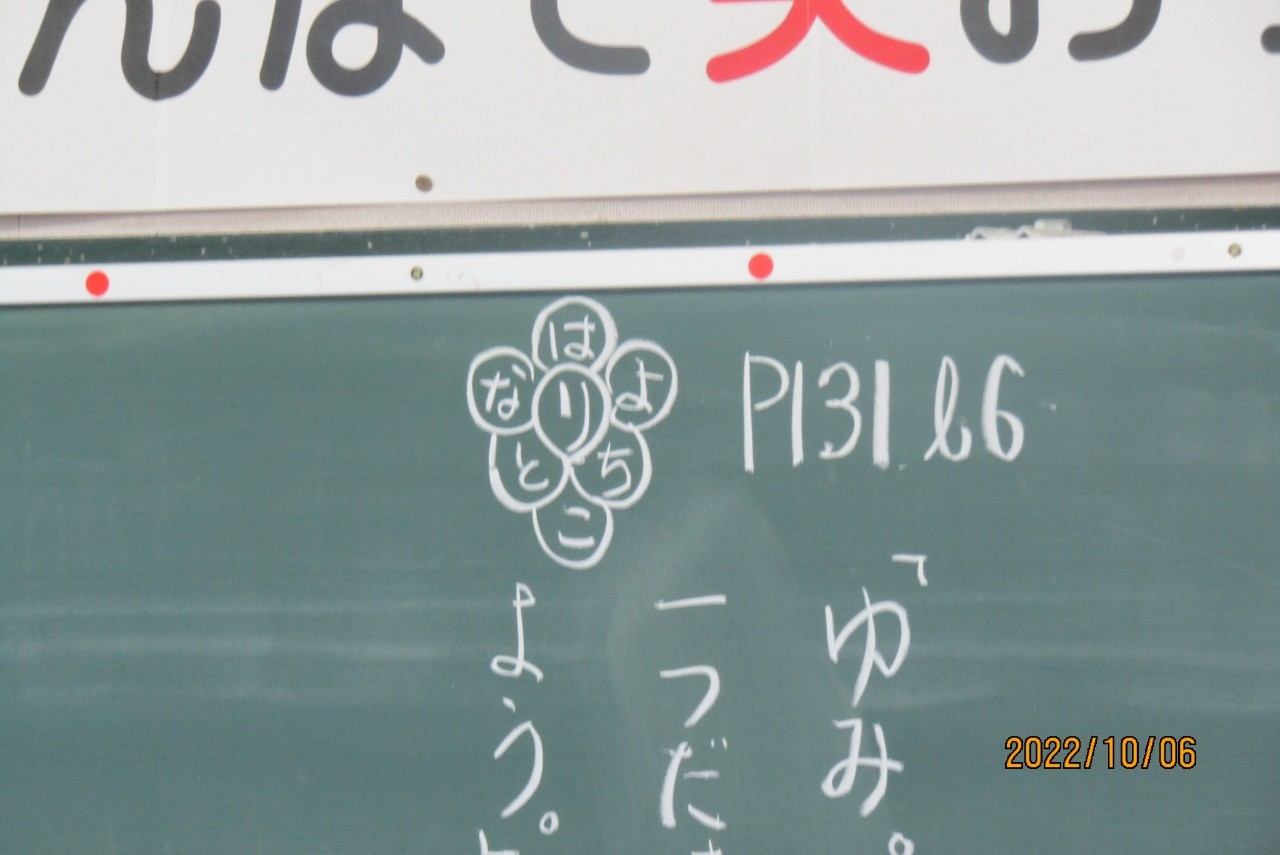学校をよくしようとする姿勢
2022-10-17 17:29:54






今日の5時間目に、1~4年生の集会がありました。これは、今週の21日に実施する遠足の説明と縦割り班の顔あわせをするためでした。このために、4年生は先週から準備をしてきました。4年生は、陸上大会壮行式の準備から始まり、今回は1日中1~3年生を引っ張る役目を任されます。昼休みに4年教室に行くと、わかりやすく説明するためにはどうすればよいのか、誰が何を分担するのかを確認している子が数人いました。いつもなら話しかけられる「優しい」雰囲気の子たちですが、今日はピンと張り詰めていました。
遠足で育ってほしい姿を担当教員から説明を受けた後、班のめあてを作っていました。4年生は、できるだけみんなの意見が取り入れられるように、ホワイトボードに一人ひとりの意見と聞き取りながらメモをしていました。その後、班としてどういう順番でどこに行くのかを計画を立てていました。「いつ」「どこで」「誰と」ということを紙に書いてみんなの意見が出しやすいように工夫している班もありました。いつも感じますが、その4年生の姿を鋭い眼差しで見つめている3年生の存在が、とても素敵でした。
今朝、登校時のあいさつを久しぶりに聞きました。数日聞いていないからなのか、とても大きな声でした。じっとみていると、今まで声を出していなかった下級生たちも、5、6年生と同じような声であいさつをしていることがわかりました。5、6年生が修学旅行でいないときに、「自分たちがこの学校を守る」という気持ちをもったのでしょう。そうした責任感をもとうとする1~4年生がいるのは、5、6年生のこれまでの姿勢をみて、自分事にする素敵な心があるからだと考えます。
5、6年生の修学旅行では、ほとんど教員の指示や注意がありませんでした。それは、今までの子どもたち自身の「トライ&エラー」の積み重ねで培われてきたものです。1~4年生も、この積み重ねをこうした活動を通して経験していってほしいと思います。
遠足で育ってほしい姿を担当教員から説明を受けた後、班のめあてを作っていました。4年生は、できるだけみんなの意見が取り入れられるように、ホワイトボードに一人ひとりの意見と聞き取りながらメモをしていました。その後、班としてどういう順番でどこに行くのかを計画を立てていました。「いつ」「どこで」「誰と」ということを紙に書いてみんなの意見が出しやすいように工夫している班もありました。いつも感じますが、その4年生の姿を鋭い眼差しで見つめている3年生の存在が、とても素敵でした。
今朝、登校時のあいさつを久しぶりに聞きました。数日聞いていないからなのか、とても大きな声でした。じっとみていると、今まで声を出していなかった下級生たちも、5、6年生と同じような声であいさつをしていることがわかりました。5、6年生が修学旅行でいないときに、「自分たちがこの学校を守る」という気持ちをもったのでしょう。そうした責任感をもとうとする1~4年生がいるのは、5、6年生のこれまでの姿勢をみて、自分事にする素敵な心があるからだと考えます。
5、6年生の修学旅行では、ほとんど教員の指示や注意がありませんでした。それは、今までの子どもたち自身の「トライ&エラー」の積み重ねで培われてきたものです。1~4年生も、この積み重ねをこうした活動を通して経験していってほしいと思います。